アメリカと日本と国際養子縁組
先日のTBSの番組「女児はなぜアメリカへ行ったのか?国際養子縁組を考える」を観た。
豊かな社会とは何だろう。ひとつには選択肢が多様であることだろう。1歳の女の子さくらちゃんが、去年アメリカにわたった。国際養子縁組で、引き取ったのは歯科医と獣医の夫婦だ。実の母親は経済的な事情から自分で育てることができないためだった。今、こうした国際養子縁組を禁止しようという動きが日本で出ている。さくらちゃんはなぜ海を渡ったのか、国内ではダメだったのか、そして国際養子縁組の禁止が本当に必要なのか、日本とアメリカで取材した。

(朝日新聞:世界各国の養子事情)
それに関連して、朝日新聞の特集「日本からも子どもが渡る『養子大国』」も興味深く読んだ。アメリカは、上図に示されるように世界有数の「養子大国」である。アメリカ国内での養子縁組が大半だが、それでも海外の子供を引き取って養う件数も多く、さらにはそれが近年、日本の子供がアメリカへ渡るケースが増加している、という内容だ。
国外から養子を迎えるのは、養子大国の米国でも少数派だ。ただ、国内では避妊や中絶が増えて望まない出産が減ったことや、シングルマザーに対する福祉施策が充実し、社会の偏見が薄れたことで、実の親が子どもを手放すことも少なくなった。新生児の養子縁組は希望する家庭の間で大変な競争になるという。国際縁組は子どもの出身国によっては待ち時間が少なく、思い直した実親が子どもを迎えに来る可能性は低い。国際養子を望む声は依然としてある。
国際縁組は、出生率が高く、経済的に苦しい途上国の子どもが先進国にもらわれるのが一般的だ。だから、日本からも米国に養子が渡っていると知って驚いた。日本は国際養子縁組のルールを定めたハーグ条約を批准しておらず、政府は海外に出る養子の数を把握していない。米国務省によると年間30~40人が米国に孤児や養子として入国している。
ここで思い出すのが、たびたび遊びに行った米国のあの家族のことである。40代の白人夫婦には子供ができなかった。そこで彼らは養子をもらうことにしたのだが、その際のプロセスが「エージェンシー」を通じて極めてスムースに行われたこと、そしてその背景にあるアメリカならではの宗教観や家族観に僕は大きな衝撃を受けたのである。アジアの国から養子をもらうための「海外ツアー」まであると言う。
その白人夫婦が養子にもらったのは黒人の赤ちゃんだった。もちろん肌・瞳・髪の色はまったく違う。現在では小学生になっているが、それくらい大きくなれば「自分が両親の実の子ではない」ことは分かる。というよりも、もっと小さいときから、そのことは聞かされて育っていた。ちなみに、産みの親が誰なのかはいまも分からない。産まれたばかりのこの子を病院の前に置いて、お母さんはそのまま行方知れずなのだと言う。

その夫婦はこの子をとても可愛がっていて、数年後もう一人子供が欲しくなった。そこで同じエージェンシーを通じて、新たに養子を引き受けた。その赤ちゃんの産みの親は、同じ地域に住む14歳の女の子。もちろん自立できる年齢ではなく、養子に出すことにした。この辺りの話はまるで数年前の映画『ジュノ』そのものである。そして、僕の知人夫婦とその女の子との面談が、エージェンシーによって設定されたそうだ。
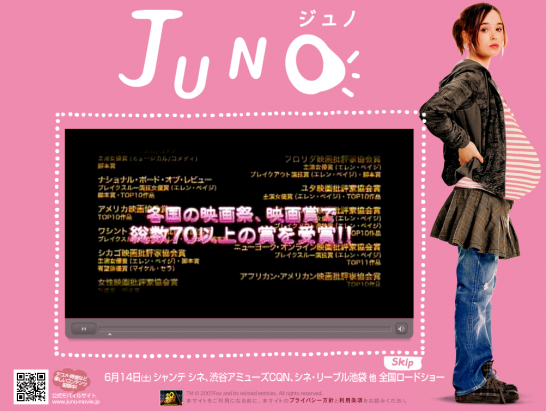
二人目の養子をもらい受け、知人夫婦はとても幸せな生活を送っていた。そしてまた数年後、もう一人子供がいてもいいかなと思っていた矢先に、今度はエージェンシー側から提案があった。当時14歳だった産みの親のあの女の子が、二度目の出産をしたのだという。まだ高校生で、もちろん自分では育てられない。だから、血の繋がった兄弟として一緒に育ててくれないか、という話だった。
夫婦は少し迷っていたが、結局はその赤ちゃんを三人目の養子として引き受けた。今は大家族となり、賑やかにそして楽しそうに暮らしている。一方で、こうした養子斡旋のシステムや、あまりにもオープンであることに、日本との大きなギャップを感じるのもまた事実である。

そしてこうした日米の違いに対する戸惑いは、恐らくは多くの日本人に共通するものであり、朝日新聞の特集後記「旅の終わりに:養子大国アメリカのいま」でも、次のように書いている。
特集が掲載された後、たくさんの読者の方から感想をいただいた。中でも多かったのが、「養子縁組に対するアメリカのオープンな姿勢に驚いた」というものだ。確かに養子縁組は、アメリカではごく当たり前の選択肢だ。取材するこちらがとまどうほど、育ての親(養親)も、養子本人も屈託がなかった。
養子縁組あっせんの市場化、子どもの養育をめぐる深刻な状況、海外へ出て行く赤ちゃん……。養子大国アメリカには「開かれた縁組」という前向きな一面だけでは語り尽くせない、様々な姿があることにも気づかされた。
僕がこの目で見たのは、アメリカ国内での養子縁組であり、少なくとも僕の目にはとても幸せそうな家族を築いているように見える。一方で養子縁組が抱える様々な問題があるのも事実だろう。しかし、不妊カップルの増加や同姓婚の拡大に伴い、養子を欲しい夫婦は世界中で増え続けている。そういうニーズがある限り、「顧客」を獲得するためのエージェンシーの競争は加速し、「養子市場のグローバル化」の流れは止まらないように思う。
Amazon Campaign

関連記事
-
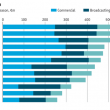
-
サッカーチームの経済学|デロイト・フットボール・マネーリーグ2016年版
今年もまたこの時期がやってきた。そう、デロイト社によるレポート "Football Money Le
-

-
非常勤講師も必要な確定申告スタート|今年からマイナンバーが義務化
2月16日から始まった今年の確定申告。一般的には、高収入のサラリーマンや、個人事業主だけに関係のある
-
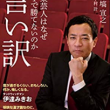
-
今年のM-1優勝はミルクボーイ|松本人志はじめ審査員の採点と評価コメントにこそ大注目
2019年、令和最初のお笑い王座を決める M-1グランプリは、決勝初出場にして史上最高点を叩き出した
-

-
町山智浩『知ってても偉くないUSA語録』は秀逸な現代アメリカ社会批評
映画評論家の町山智浩をご存知だろうか?そして、彼の秀逸な現代アメリカ観察記をご存知だろうか?そんな週
-

-
藤井聡太・新棋聖誕生|史上最年少タイトル獲得の瞬間を目撃したか?
藤井聡太七段、渡辺明棋聖を3勝1敗で下し、史上最年少で初タイトルを奪取した(時事通信社)。僕らは今、
-

-
ニューヨーク・タイムズが選ぶ、今年絶対に行きたい世界52ヶ所:2016年版
さて今年もこのシーズンがやってきましたね。ニューヨーク・タイムズ紙が発表する「今年絶対に行きたい世界
-

-
米国人一家と英国一家が美味しい日本を食べ尽くす
ちょっぴり巷で評判の『米国人一家、おいしい東京を食べ尽くす』を読んでみたら、これが思いの外おもしろか
-

-
法律改正、脳死判定、臓器移植、そしてコーディネーター
先日、「6歳未満女児の脳死判定、臓器提供へ:国内2例目」というニュースがあった。そして「心臓と肺を男
-

-
Amazon.com の勢いが止まらない|サイバーマンデーで過去最高売上を記録
株価上昇が続くアメリカ経済の中でも、Amazon.com の勢いはひときわ目を引く。下のグラフを見れ
-

-
スタンフォード大学に集まる若き経済学者たち
先週のニューヨーク・タイムズ紙の記事 "How Stanford Took On the Giant










