山に登るということ:登山と遭難とそして救助
2008年のマンガ大賞にも選ばれた、山岳漫画『岳』。いまさら言うまでもないが、これものすごく胸を打つマンガなのである。なぜ人は山に登るのか、それも死と隣合わせの山に。そしてそんな人を救助する側は、どんな思いを抱いて山に居続けているのか。日本国内でも雪山やスキー場での遭難が相次ぐ昨今、冬に山に登るということの危険を再認識するという意味でも、読み返されてよい漫画ではないかと思う。

photo credit: TomFahy.com via photopin cc
さて、「最強のクライマー夫婦物語『凍』と、山岳救助漫画『岳』」にも書いたとおりなのだが、このマンガ『岳』の後にぜひとも読んで欲しいと思っているのが、沢木耕太郎の『凍』だ。沢木の作品をいくつも好んで読んできた僕にとっても、これは絶対におすすめできる一冊。世界最強とも讃えられた日本人クライマー山野井泰史が妻・妙子と挑んだヒマラヤの難峰ギャチュンカン。登頂後に雪崩に巻き込まれ視力を失い、食料も尽きてもはやこれまでかと思っていたところ、妙子の直感もあって二人で奇跡の生還を果たす。その壮絶なまでの登山を、彼らの生活に密着した沢木耕太郎の筆が静かに熱く記録したものである。
そして、その同じ登山を山野井が自ら振り返ったのが以下の『垂直の記憶』だ。ぜひ沢木の『凍』と読み比べて欲しい。
そして最近僕が読んだのが、その山野井泰史の近刊『アルピニズムと死 僕が登り続けてこられた理由』だ。世界最強のクライマーは同時に「天国に最も近い男」と呼ばれ続けていた。それは誰よりも高いところに登るからではなく、誰よりも危険な登山をし、いつ死んでもおかしくないと囁かれていたためである。しかし、そんな山野井がギャチュンカンを始めとするいくつもの絶体絶命の状況から生還し続けたのには理由がある。それを自ら振り返ったのがこの『アルピニズムと死』の内容だ。
山野井と、山で死んだ彼の多くの戦友たちとでは何が違ったのだろうか。もちろん運もあれば精神力もある。それと同時に、圧倒的な準備、数多くの技術、積み重ねた経験、そしてそこから導き出される感覚や想像力、そういうありとあらゆるものを総動員して、これまでなんとか生き抜いてきた。登山やスキー・スノボ用具の発達で、近年では多くの人にとっても雪山が身近なものとなったのは間違いないだろう。しかし、最近相次いだ遭難事故が示すように、山に簡単な事など何一つない。そういう背筋が伸びる思いをさせてくれる本書もまた、登山ブームといわれるいま、もっと読まれてもよい内容と言えるのではないだろうか。山に登り始めたばかりの人、そしてこれから登山を始めてみたいと思っている人にとってはとくに、真摯に読んでおきたい一冊である。
Amazon Campaign

関連記事
-
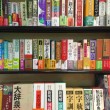
-
いま国語辞典がおもしろい|10年ぶりの大幅改訂による最新版あいつぐ
さて、「2020年、本ブログで最も売れたこの1冊」でも紹介したように、昨年の一年間でもっとも売れたの
-

-
敗れざる者たち|藤井聡太に失冠したトップ棋士たちの言葉
もちろん、もう読みましたよね?藤井聡太二冠を表紙にすえ、初めて将棋を特集したスポーツ雑誌Number
-

-
正月の風物詩・箱根駅伝が今年もおもしろい
新年明けましておめでとうございます。新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、ステイホームの継続と静かな
-

-
日本将棋マネーリーグ|今年も賞金ランク首位は豊島将之竜王、藤井二冠は?
先日は毎年恒例の「欧州サッカー・マネーリーグ」が発表され、今年もスペインのFCバルセロナが収入ランキ
-

-
東京藝大で教わる西洋美術の見かた|基礎から身につく「大人の教養」
2022年1月3日から、BSイレブンで新番組「東京藝大で教わる西洋美術の見かた」が始まる。これはぜひ
-
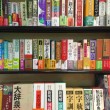
-
辞書編纂者・飯間浩明の仕事の流儀プロフェッショナル
先日NHKで再放送された「プロフェッショナル仕事の流儀」をご覧になっただろうか。「言葉の海で、心を編
-

-
Kindle電子書籍で手に汗握って読む、箱根駅伝をより面白くするこの3冊
いまや国民的イベントにまで人気が拡大した、正月の風物詩・箱根駅伝。僕も含めて毎年楽しみにしている人は
-

-
日本囲碁マネーリーグ|賞金ランク首位・国民栄誉賞の井山裕太
さてさて、1-2月にかけては毎年、それまでの一年間の各種ランキングが発表されることが多い。僕自身が毎
-

-
Kindle電子書籍でわくわく読む、角川書店の初心者向け数学シリーズ
今年はますます電子書籍市場の拡大に拍車がかかりそうだ。「2018年には米国と英国で紙書籍を追い抜くか
-

-
中央アジアを舞台とした傑作漫画『乙嫁語り』|最新刊の精緻な描写が素晴らしい
待望の『乙嫁語り』の最新第10巻が発売された。さっそく読んだのだが、これまた素晴らしい生活描写と風景














