連邦最高裁判事9人が形づくるアメリカの歴史
下の写真がアメリカ連邦最高裁判所だ。各種ニュース等での報道の通り、今回はこの最高裁が、これまで人工妊娠中絶を合憲だとしてきた判例を約半世紀ぶりに覆すことになった。すでにアメリカ各地では、そしてこの連邦最高裁周辺においても、大規模なデモや反対運動が始まっている。
(NHK)アメリカの連邦最高裁判所は、人工妊娠中絶をめぐり「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとした49年前の判断を覆しました。今後、全米のおよそ半数の州で中絶が厳しく規制される見通しとなり、中絶容認派は強く反発する一方、中絶反対派からは歓迎の声が上がるなど国内の受け止めは大きく分かれています。

なぜ最高裁自らが、自分たちの昔の判断を覆すような異例のこととなったのか? それは、このアメリカ連邦最高裁の判事の構成がここ数年で大きく変わったからに他ならない。9人しかいない最高裁判事だが、これまでは、リベラルと保守が、5-4 または 4-5 というような拮抗する形で構成されてきた。そしてこの最高裁判事は終身制であるため、本人が亡くなるか、もしくは自ら退任した場合にのみ、新たな判事が補充されるのだ。そして、その判事を指名するのは大統領の権利となっている。
つまり、いくら大統領の任期が長かったとしても、ひとりも判事を指名できないこともあれば、短命に終わった政権であっても複数人の判事を指名する機会を得ることもある、ということになる。その典型例が、トランプ大統領時代の保守党であり、一期4年間で終わったトランプ大統領であったが、なんとこの間に3人もの判事を後任指名することができたのだ。
アメリカ大統領がもつ大きな権限の中でも、この連邦最高裁の判事指名は極めて大きい。なにしろ、まさにこのトランプ元大統領のように、自分が大統領職を退いたあとでも、将来にわたって長期的にアメリカ社会に影響を与えることができるのだから。
しかし、こうして選ばれたたった9人の連邦最高裁判事の素顔は驚くほど知られていない。アメリカで国を二分するほど紛糾した議論となった過去がある、黒人や女性の権利など、最終的にはこの9人がまさにジャッジを下してきたのだ。そんな彼らの仕事ぶりや人となりを追った傑作ノンフィクションがこちらの『ザ・ナイン』である。アメリカ建国の精神にのっとり、合衆国憲法と対峙し、そして時代に合わせた決定的な判断を下してきた、エリート中のエリートである9人の、挑戦と奮闘そして苦悩と葛藤がここにある。いま、半世紀ぶりに最高裁判例が覆り、アメリカ社会は揺り戻す方向に大きく舵が切られた。その背景には、この9人の構成バランスが崩れたことが挙げられ、しかもそのバランスが元に戻るには相当長い時間を覚悟しなくてはならないのだ。こうしたアメリカの、国づくりの力学を理解するためにも、本書は格好のテキストになると言えるだろう。これまで謎に包まれてきた法廷の裏側に迫る、今こそもっと読まれて欲しい、異色の力作なのだ。
保守派の台頭と9人の最高裁判事(ザ・ナイン)。人種、性、妊娠中絶、福音派、大統領選挙など、巨大国家の行方を定める判事たちの知られざる闘いを追った傑作法廷ノンフィクション!ニューヨーク・タイムズ年間最優秀図書。
Amazon Campaign

関連記事
-
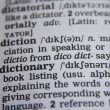
-
【おすすめ英語テキスト】英語を英語で理解する、上級英単語集が半額以下のセール
現在実施中の、Amazon Kindle【40%OFF以上】高額書籍フェア には、ちょっとお値段が高
-

-
綻びゆくアメリカと繁栄から取り残された白人たち
2014年に翻訳出版された『綻びゆくアメリカ―歴史の転換点に生きる人々の物語』に今また注目が集まって
-

-
愉しく美味しく走ろう!南魚沼グルメマラソンを応援してきた
本日のKindleセール商品は、『ウルトラマラソンマン 46時間ノンストップで320kmを走り抜いた
-
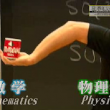
-
数学ミステリー白熱教室|数学と物理学の驚異のつながり
「NHK『数学ミステリー白熱教室』本日最終回をお見逃しなく」でも書いたように、先週末でNHKの「白熱
-

-
イェール大学出版局 リトル・ヒストリー|若い読者のための「アメリカ史」のすすめ
以前にも紹介したことのある、「イェール大学出版局 リトル・ヒストリー」のシリーズ。いまのところ5冊が
-

-
若き研究者フィギュアスケート町田樹のスポーツ文化論
2022年の冬季北京五輪の開幕も近づいてきた。ウィンタースポーツの代表例のひとつが、フィギュアスケー
-

-
アメリカ地方自治体の分断:富裕層による独立運動
先日のNHKクローズアップ現代を興味深く視た。「“独立”する富裕層 ~アメリカ 深まる社会の分断~」
-

-
【おすすめ書籍】ハーバード数学科のデータサイエンティストが明かす恋愛ビッグデータの残酷な現実
アメリカでベストセラーとなった一冊 "Dataclysm" がようやく翻訳出版された。これは人気出会
-

-
戦略アナリストが支える全日本女子バレー|世界と互角に戦うデータ分析術
女子バレーボールのワールドカップもいよいよ終盤戦。リオデジャネイロ五輪への出場権をかけて瀬戸際のニッ
-

-
町山智浩『知ってても偉くないUSA語録』は秀逸な現代アメリカ社会批評
映画評論家の町山智浩をご存知だろうか?そして、彼の秀逸な現代アメリカ観察記をご存知だろうか?そんな週











