バッタの大群襲来|書籍『バッタを倒しにアフリカへ』が現実に
以前に「若き昆虫学者のアフリカ|いまこそ昆虫が面白い」でも書いたように、昨今にわかに昆虫ブームなのはご存知の通りだ。香川照之がハジけた解説をするNHK番組「昆虫すごいぜ!」がおもしろ楽しいだけでなく、そのご昆虫展へと広がりを見せたり、昆虫食に対する関心が急速に高まったりと(例えば、書籍『昆虫は美味い!』や、記事「渋谷パルコで虫ランチ」等)、ちょっと前と比べると、明らかに昆虫を巡る環境と認識が激変しているのだ。
さて、そんななか飛び込んできたのが、この緊急ニュースだ(ロイター「バッタの大群が襲来、ソマリアで数十年ぶり最悪の被害」)。
アフリカ東部のソマリアで21日、サバクトビバッタの大群による被害が拡大した。同国ではすでに、何万ヘクタールもの農地が被害を受けている。サバクトビバッタはすでに、国内の数万ヘクタールもの農地や放牧地を破壊。過去25年間で最悪の被害をもたらし、家族を養うための食料を、多くの人が失った。バッタの大発生はすでに、国連食糧農業機関(FAO)の予測を超えている。

そして、このニュースを聞いてまっさきに思い出したのが、サバクトビバッタの研究者として第一人者に間違いないであろうと思われる、通称「バッタ博士」の異名をとる、前野ウルド浩太郎氏である(ちなみに、なぜ「ウルド」なのかは、彼の会心の著書『バッタを倒しにアフリカへ』にその経緯が明らかにされている)。さて、本書は以前に「若き昆虫学者のアフリカ|いまこそ昆虫が面白い」で激オススメしたように、めちゃくちゃ面白いんです。その研究内容と波乱万丈のアプローチは、まさに手に汗握る傑作の物語であり、文中いや道中どうしても読んでいるこちらまで感動を抑えられない、そんなアツい研究者による一冊なのだ。今回、数十年ぶりにバッタの大群が大発生し、世界的にも問題となっている今こそ、絶対に読んで欲しい内容である。
「大学院を出て、ポスドクとして研究室にいた頃は、安定した職もなく、常に不安に苛まれていました。博識でもなく、誇れるような実績もない。友達と楽しく飲んでいても、トイレにたったときに研究の手を止めた罪悪感に襲われる日々でした。なので、一発逆転を狙おうと」
日本ではスーパーで売っているタコの産地として知られるモーリタニア。バッタ研究者だった前野さんは、思い立って一路モーリタニアへ。このたび、かの地で経験した一部始終を記した『バッタを倒しにアフリカへ』を出版した。
「サバクトビバッタはアフリカで数年に1度大発生し、農作物に大きな被害を与えています。私はこのバッタの研究者なのに、人工的な研究室で飼育実験ばかりしており、野生の姿を見たことがなかった。自然界でのバッタを観察したいという気持ちもありました」
本書は、現地の言葉(フランス語)もわからずに飛び込んだ前野さんの冒険の記録でもある。
売り上げランキング: 905
そして以下の一連の昆虫シリーズ本は、虫好きにはもちろんのこと、ちょっと怖いものを見てみたいムシ初心者の方にまで、ものすごくおすすめですよ。
Amazon Campaign

関連記事
-

-
TSUTAYA運営の市立図書館に続き、今度は学習塾ノウハウを公教育に導入:いま話題の佐賀県武雄市に行ってきた
佐賀県武雄市がまた新しい取り組みを始めたようだ。 (NHKニュース)佐賀県武雄市は、来年の春から公
-

-
出版不況なのに「TikTok売れ」で緊急重版|あの実験的小説の新しい売り方・売れ方
先日紹介した書籍『10代のための読書地図』は、本当におすすめなので、ぜひまだの方には読んでみて欲しい
-

-
東京オリンピック野球で導入された変則的決勝トーナメント
東京オリンピックの野球種目は、準々決勝でアメリカを倒し、準決勝で韓国を破った日本が、堂々の決勝進出を
-

-
将棋タイトル王位戦第2局|藤井聡太七段が木村一基王位に大逆転勝ち
いやあ、昨日の王位戦、ライブ中継で観た方は、これはもうとんでもないもの見てしまった、という感じではな
-

-
ラグビー日本代表が強くなった理由|エディー・ジョーンズのコーチング
冬のスポーツ風物詩と言えば、箱根駅伝に加えて高校サッカー、そして大学ラグビーである。そんなラグビーの
-

-
Kindle電子書籍で手軽に読む高野秀行の探検記シリーズは、フィクションかと思うほどの強烈ノンフィクション
高野秀行という作家はものすごく強烈な個性を放っている。「高野秀行はセンス抜群の海外放浪ノンフィクショ
-

-
テニスプロはつらいよ|トッププレイヤー錦織圭とその他大勢の超格差社会
2014年の全米オープンテニスで日本人初のグランドスラム決勝進出を果たした錦織圭。その後の凱旋ツアー
-

-
辺境ライター高野秀行の原点『ワセダ三畳青春記』の「野々村荘」こそ日本最後の秘境
「高野秀行はセンス抜群の海外放浪ノンフィクション作家」にも詳しく書いたように、辺境ライターこと高野秀
-
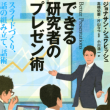
-
できる研究者の英語プレゼン術|スライド作成からストーリー展開まで
以前に紹介した、ポール・シルヴィア著の『できる研究者の論文生産術』は素晴らしい一冊である。著者は20
-

-
2019年ノーベル経済学賞は開発経済学者3氏と貧困解消に向けた実験的手法に決定
2019年のノーベル経済学賞受賞者が発表された。受賞者は、マサチューセッツ工科大(MIT)のバナジー















