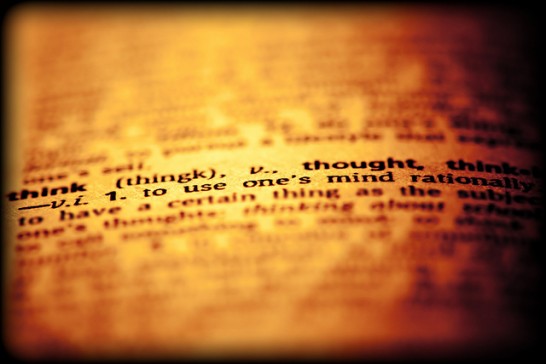【TEDトーク】国語辞典のすすめ:辞書編纂の面白さは、英語も日本語も同じ
公開日:
:
最終更新日:2021/01/31
オススメ書籍
先日のNHK-Eテレ「スーパープレゼンテーション」に、辞書編纂者のエリン・マッキーンが登場。そのトークを興味深く聞いた。
1971年生まれ。8歳のとき、Oxford English Dictionaryの辞書編纂者Robert Burchfieldに関する新聞記事を読み、辞書編纂の仕事に興味を持つ。93年、シカゴ大学で言語学の学士を取得。大学を卒業後、教育書籍の出版社で子ども用英語辞書の編集に携わった後、04年、Oxford University PressでThe New Oxford American Dictionaryの編集責任者となる。08年、Reverb Technologies 社を起業し、09年、オンライン辞書Wordnikを立ち上げる。アメリカの新聞や雑誌に、言葉に関するコラムを寄稿している。趣味はビンテージの布地を集め、洋服を縫うこと。また、彼女が綴る「A Dress A Day」というファッション・ブログが人気で、13年、「The Hundred Dresses」というファッション事典も出版した。
彼女のトークの中でひときわ印象に残ったのが、辞書をつくっていると言うと「間違った言葉づかいを正す警官」をイメージする人が多いけれど、決してそんなことはないということ。むしろ、なるべく多くの言葉を辞書に載せるために、「いつも新しい言葉を探している漁師」のような仕事なのだと。
なぜこのエピソードに僕が惹きつけられたかと言えば、それはやはり同様のことを、日本語の辞書づくりの天才・見坊豪紀(通常ケンボー先生)が言っていたからに他ならない。洋の東西や言語の違いにも関わらず、辞書編纂というある種の特殊作業に携わる人たちが持つ感性に共通する部分を見つけたことに、なぜか思わずうれしくなってしまったのである。
日本語の辞書編纂といえば、本屋大賞第一位をとったベストセラー、三浦しをん著『舟を編む』がまだ記憶に新しい。松田龍平と宮崎あおい主演で映画化もされ、これがまたなかなか素敵な映像となっていたので、まだご覧になっていない方には、ぜひともオススメしたい。
さて、見坊豪紀が辞書編纂の哲学としたのが、「辞書は言葉の鑑であると同時に鏡であれ」ということ。つまり辞書には、言葉を正す「鑑」の性格と、言葉の実態を映す「鏡」の性格の両方が備わっており、そのどちらを重視するかが辞書づくりの重要な編纂方針となってくるということだ。そして、とくに見坊が重視したのが現代語の変化をいち早く辞書に反映させようという鏡としての役割であったのである。
だからこそ、見坊豪紀が手がけた三省堂国語辞典(通称サンコク)では今もその哲学が貫かれ、いちはやく新語や若者言葉などを収録しており、それが他の多くの辞書とは決定的に異なる特徴となり、「新語に強い」という定評を得ているのだ。「学校で教えて欲しいおすすめ国語辞典の選び方・使い方・遊び方:複数の辞書を比較して使い分けよう」でも詳しく書いたように、辞書にはそれぞれ個性がある。だからこそ、目的に合った一冊を選ぶこと、そして出来れば複数の辞書を用意して使い分けることが大事になってくるのである。
そんな三省堂国語辞典が、それでは見坊亡き後、どのように編纂されているのかについては、まさにその作業のまっただ中にいる飯間浩明の『辞書を編む』の描写が大変に興味深い。街を歩き、新しい店の看板に斬新な日本語を見つけてはメモに取り、ファストフード店で高校生の会話に耳を傾け若者特有の新語を採集する。下手すりゃタダの怪しい中年に間違われかねない、そんなキケンをものともせず、新しい日本語との出会いを探し続けるさまは狩人のそれに近い。なにしろ文字通りの、新語ハンティングなのだから。
さて、そんな辞書作りの天才にして、今なお三省堂国語辞典の編纂方針に大きな影響を与え続ける見坊を語るには、その終生の同志でありながら、人生の途中で袂を分かったもう一人の天才・山田忠雄という人物を語らないわけにはいかないのである。「ケンボー先生の三国と山田先生の新明解」で紹介したように、東大同級生にして元々は同じ一つの辞書作りに取り組んでいた見坊と山田の二人は、次第にそれぞれの理想が違う方向を向いていることに気付き、そしてある瞬間を境に決別することとなってしまう。1972年の1月9日という一日に、ふたりの間に一体何があったのか、その日本辞書史上最大の謎に迫ったのが、この『辞書になった男 ケンボー先生と山田先生』という読み応えのある一冊だ。めちゃくちゃ面白い超弩級のノンフィクション。少しでも辞書というものに関心があるのなら、ぜひとも読んで頂きたい(参考:いま日本で最も売れている「新明解国語辞典」の誕生秘話)。
というわけで、TEDトークで英語の辞書編纂者の話を聞いたことがきっかけで、改めて言葉という生き物の面白さと、辞書作りの奥深さに気付かされたわけである。そして繰り返しになるが、「辞書はどれも同じようなもの」では決してないのである。辞書編纂に携わる人の哲学と個性が存分に発揮された、かけがいのない一冊なのである。どの辞書にどんな特徴があるのかを、真面目にでもカジュアルに解説してくれるのが、この『学校では教えてくれない!国語辞典の選び方』である。「学校で教えて欲しいおすすめ国語辞典の選び方・使い方・遊び方:複数の辞書を比較して使い分けよう」でもイチオシした一冊であるが、辞書芸人サンキュータツオの熱のこもった筆から、彼がいかに国語辞典を愛しているのかがよく分かる内容。これもものすごく面白い、おすすめの辞書本です。
Amazon Campaign

関連記事
-

-
チェス界のモーツァルト、天才ボビー・フィッシャーの生涯が待望の文庫化
伝説的なチェスプレイヤー、ボビー・フィッシャーの生涯を記録した傑作ノンフィクション『完全なるチェス』
-

-
サッカー日本代表W杯開幕戦:日本のサッカーを強くする25の視点
あと数時間で、日本対コートジボワール戦のキックオフ。おそらく今回も相当大勢の日本人が、このときばかり
-

-
欧州サッカー「データ革命」|スポーツを科学する最前線ドイツからの現地レポート
先日書いた「錦織圭の全豪オープンテニスをデータ観戦しながら応援しよう|IBMのSLAMTRACKER
-

-
連邦最高裁判事9人が形づくるアメリカの歴史
下の写真がアメリカ連邦最高裁判所だ。各種ニュース等での報道の通り、今回はこの最高裁が、これまで人工妊
-

-
最年少プロ棋士・藤井聡太とAI将棋の時代|人工知能が切り拓く新たな地平
ついにストップした藤井聡太四段の連勝記録。しかし、史上最年少でプロ棋士となってから、これまで29連勝
-
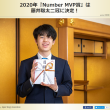
-
将棋棋士初の栄冠|『Number MVP賞』は 藤井聡太二冠に決定
先日は以下のエントリでも書いたように、2020年は間違いなく藤井聡太の一年でもあり、将棋棋士がアスリ
-

-
絶対に負けられないサッカー・ワールドカップの舞台裏:スポーツブランドのもう一つの闘い
「絶対に負けられない戦い」に直面しているのは、もちろんサッカー選手だけではない。監督やスタッフ等もそ
-

-
プレゼンを準備する前に繰り返し読みたいおすすめの一冊『TED TALKS』
話題の一冊『TED TALKS』を読んだ。ご存知いまや圧倒的なプレゼンスを獲得したTEDカンファレン
-

-
NHK「最後の講義」物理学者・村山斉を見逃すな
先日のNHK「最後の講義」みうらじゅんが圧倒的に面白かったのは既にお伝えの通りだが、2/20(水)放
-
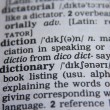
-
今こそ再び学ぶ『英語の読み方』|読めるか読めないかそれが問題だ
英語学習に関する書籍というのは、それこそ書店に溢れていて、玉石混交でどれを選んだらいいのか分からない